チベット問題への私的見解
| チベット問題への私的見解 |
15.SEP.10 |
1.もし私がダライ・ラマならば、即身仏になる。 私の家から、車で西方へ40分ほど走った山間部に、両界山横蔵寺がある。ここに有名な即身仏ミイラが安置されている。今から200年ほど前、横蔵の地に生まれた妙心上人は、37歳の若さで死を悟り、衆生の救済を願い、富士山麓の洞窟に籠もり断食し、さらに水を絶ち、30日後、生きながらに入定された。その後、妙心上人のミイラは、生誕の地の横蔵に移され、山間の素朴な寺の中に、舎利仏として祀られることになった。私はラサのポタラ宮の中の豪壮華麗な歴代ダライ・ラマのミイラの棺を見ながら、ふと横蔵寺の妙心上人のミイラを思い出し、帰国後すぐに拝観に行った。  横蔵寺の舎利堂では、妙心上人のミイラをガラスケース越しではあるが、間近に見ることができる。私はそのお姿を拝観し、衆生の救済のため自らの命を絶った日本の仏僧のすがすがしさを感じた。横蔵寺のミイラは即身仏である。つまり妙心上人は自分の意思で生きたままミイラになったのである。 香港フェニックステレビの論説員の梁文道氏は、「今、問題なのは、ダライ・ラマを最も嫌っているのは北京中央政府ではなくて、チベット自治区政府の特にチベット人関係者だということです。彼らは、もしダライ・ラマが戻ってきて、チベットにある程度の自治がもたらされることになったら、自分たちの利益が損害を受けることを恐れている。また現在の時点で本当に困っているのは北京当局ではなくて、ダライ・ラマです。ダライ・ラマは存命中に問題を解決したがっている。というのも、ダライ・ラマが亡くなれば海外のチベット独立運動には象徴がいなくなり、ばらばらになってしまうからです」(ふるまいよしこ著 「中国新声代」 集広舎刊 P.158)と発言している。 私は梁文道氏のこの視点は、現在のチベット問題を明確に描きだしていると考えている。しかもさらに切実な問題は、ダライ・ラマがすでに70歳を越え、死期を悟る年齢に近づいていることである。もしダライ・ラマがダラム・サラなどチベット外の地で死を迎えたならば、ダライ・ラマはミイラになってポタラ宮で歴代ダライ・ラマと共に眠ることはまず不可能であろう。チベット仏教の伝統を守るには、ダライ・ラマはミイラとなってポタラ宮に祀られなければならない。またダライ・ラマも切にそのことを願っているにちがいない。 ダライ・ラマは、「私は釈尊―その英知は完全にして無謬である―によって、初めて説かれ、さらには私たちの時代に至り、インドの聖者であり指導者であったマハトマ・ガンジーによって実践された、いわゆる“非暴力の教義”の、不動の信者である」(「チベット わが祖国」 木村肥佐生訳 中央公論新社刊 P.23)と語り、「武器を用いず、真実と不屈の決意という強力な武器によって自由と正義のために戦う」(「ダライ・ラマ自伝」 山際素男訳 文春文庫刊 P.417)と主張している。また彼はノーベル平和賞受賞時に、「この受賞を、非暴力という手段で変革を実践するという輝かしい伝統の創始者である、マハトマ・ガンジーに捧げます」(「愛と非暴力」 三浦順子訳 春秋社刊 P.1)とスピーチしている。これらの著述から、当然のことながらダライ・ラマの根本思想は、非暴力であるということができる。 ダライ・ラマは残された時間内で、非暴力を貫き、チベットに帰還し、ミイラとしてポタラ宮に安置されなければならない。現状の闘争方針のままでは、これは実現不可能である。私がダライ・ラマならばこの閉塞した事態を打開するために、ハンガーストライキ戦術を取る。もちろんそのハンガーストライキの結果、即身仏になることも辞さない。否、即身仏になることを目指す。そして同時にチベット内の多くの僧侶にハンガーストライキへの参加を促す。私は、「ダライ・ラマの取りうる最高戦術は即身仏になることを辞さないハンガーストライキである」と考える。そうすればラサに帰ることもできるし、ミイラになりポタラ宮に祀られるし、なによりも非暴力で戦いに勝つことができる。 ダライ・ラマ自身も、「チベット人一般大衆が、私に対して多大な信仰と希望を抱いているのは、周知のことである。私の方でも、これらチベット人の幸福のためなら、自分にできることはなんでもやろうと、覚悟を決めている」(「チベット問題」 山際素男著 光文社新書 P.165)と、その決意のほどを語っている。また「私は、やがて死すべき運命の単なる人間であり、わが支配者の不滅の精神の一道具に過ぎない。それだから、死を免れ得ない人間の肉体一個の最期は、さほど重要な結果ではない」(前掲 「チベット わが祖国」 P.247)と、その死生観を語っている。 なお、私はチベット問題について語ろうとする者にとっては、阿部治平先生の大著「もうひとつのチベット現代史」(明石書店刊)が必読の書であると考えている。私は以下に、この阿部先生の書に、最大限の敬意を払いながら、私見を述べて行きたいと思っている。 阿部先生は同著(P.506)で、「あさはかなチベット認識はチベット人の生活や文化や仏教へのロマンチシズムと同情心を生む。チベット人にガンジー的非暴力主義をとるようにと説いたり、チベット人地域を非武装地帯にしたらどうかと真剣に提案する人も出てくる。しかし、チベットの現状はかるがるしく発言できる状態にはない。…何かチベット人に忠告するような思惟や言動はなによりも非現実的である。そしてそれは少数民族には統治能力がないとか、はては迷信深いの無知だの汚いのという偏見と紙一重である」と、主張されている。 この阿部先生の主張を熟読玩味した上でも、なお私はダライ・ラマに非暴力で戦い、即身仏になることを提言する。またその提言が、多くのダライ・ラマ尊崇者から、不遜であるという非難の声を受けるであろうことも覚悟の上である。さらに空理空論であるとの批判があるだろうことも承知の上である。それでもなお、私はダライ・ラマに即身仏になることを提言する。なぜなら私は、ダライ・ラマが死をも辞さない宗教家であり、彼がチベット人民を熱烈に愛しているリーダーだと確信しているからであり、ダライ・ラマが50年来の「守りの戦術」から、大胆な「攻めの戦術」に転換し、この戦いにおいて主導権を握らなければ、到底、現状は打破できないと考えているからである。 2.もし私がダライ・ラマならば、亡命しなかった。 1959年3月、ダライ・ラマはインドに亡命した。ほとんどの本が、このダライ・ラマの亡命について、疑問の余地のない行動として肯定している。今回のチベット調査旅行中、ふと私は「果たして、この亡命は正しかったのか。他に選択肢はなかったのか」と、疑問を持った。なぜなら私は若きころ、学生運動のリーダーの一員として多くの修羅場をくぐってきたが、そのとき常に自分に言い聞かせていたのは、「どんな事態になっても、体を張って部下を守り抜くこと」であった。そんな青臭い正義感を持っていたので、何度となく大怪我をしたし、死にかけたこともあった。もちろん大きな被害をうけたのは、わが組織が非暴力を旗印に掲げており、私たちは丸腰で闘ったからでもある。だから私はリーダーとしての自分の経験に照らし合わせて、ダライ・ラマが多くのチベット人を残して亡命してしまったことに、素朴な疑問を持ったのである。しかし同時に私は、ダライ・ラマほどの人物だから、きっと「確たる決意と巻き返しの戦略戦術」を胸に秘めて亡命したにちがいないとも思った。 私は日本に帰国して、ダライ・ラマ自身の言葉を記録した数冊の本を読み、その中で「亡命の理由と巻き返しの戦略戦術」に該当する個所を必死に探した。その結果、どこにもそれらを見出すことはできなかった。それらに近い文言を以下に書き出しておくが、もし私がダライ・ラマならば、あの時点でラサに留まり、非暴力・不服従のマハトマ・ガンジーに倣って、ハンガーストライキで闘っただろう。もちろん多くの敬虔な僧侶を巻き込んで、一大大衆運動に盛り上げていっただろう。残念ながら、ダライ・ラマは3月17日夜、変装してノルブリンカ宮殿を抜け出し、インドへ向かった。ダライ・ラマの亡命後、ノルブリンカ宮殿を取り囲んでいたチベット人たちは、中国軍に蹴散らされ、公式には「人民解放軍はわずか1千余の兵力で武装叛徒5300余人を殲滅し、うち545人を殺し、4800人を傷つけるか捕虜とした」(前掲 阿部著 P.169)という結末を迎えたのである。ダライ・ラマの捨て身の亡命は、結果としてノルブリンカ宮殿を取り囲んだチベット人を救うことはできなかったのである。私は、「亡命という行動が、本当にもっともよい戦略戦術だったのか」を、今、真摯に考え直してみるべきだと思う。 1910年、ダライ・ラマ13世は、清軍のラサ侵攻を前に、インドに亡命した。ところがこのときは、翌年に辛亥革命が起き、清朝そのものが自壊し始めた。ダライ・ラマ13世はただちにラサに戻り、清軍をラサから追い出し、1913年には独立を宣言した。ダライ・ラマ14世と彼を補佐するチベット政府高官たちには、おそらくこのときの成功体験が色濃く残っていたのではないか。そして今回の亡命を、短期間で舞い戻ることが可能であり、一時的な避難程度に捉えていたのではないか。ダライ・ラマ14世とその取り巻きは、亡命生活が半世紀を超えるとはまったく予想していなかっただろう。 現在、1959年のこの事態については、チベット人の階級闘争であり、ダライ・ラマが属する農奴主階級、腐敗した貴族や僧侶などが、人民解放軍に支えられた農奴や一般民衆に打ち倒され、結果としてダライ・ラマが亡命せざるを得なくなったという説が強い。そのような見方をすれば、放逐されたに等しいダライ・ラマが、ラサに帰ることを望む正当性はないのではないか。 ≪ダライ・ラマ14世の亡命の理由≫ ・「1959年、われわれの歴史を通じて未だ経験したことがないほどの抑圧下にチベット全土が曝された時、私はついに亡命を余儀なくされたのである。チベットの民族と文化を守ってゆくためには、そうせざるを得なかったのだ」(前掲 「チベット問題」 P.161)。 ・「私が決心するに当たって、私が持っていた明確な世俗的指針がただ一つあった。それは、もし、私が留まることを決意すれば、わが国民や私のもっとも親密な友人たちの嘆きを、むしろさらに増大する結果になるであろう、ということであった。私は出発する決心をした」(前掲 「チベット わが祖国」 P.248) ・「私はいま、静かに回想してみて、あの事件の瞬間から、私があのまま留まっていたとしても、わが国民のために、私ができることはもはや何もなかったであろう。しかも、中国側は最後にはきっと私を捕えたことであろう。私にできることは、インドに赴いて、インド政府に亡命者としての保護を要請し、そしてインドにおいて、各地に散在するわが国民のために、希望の火が消えないよう、私自身、この身を捧げて専念することだけだった」(「チベット わが祖国」 P.268)。 ・「超自然現象的な忠告はわたしの理論と合致していた。脱出だけが群衆を解散させる唯一の方法だとわたしは確信した。わたしが宮殿にいさえしなければ、人びとは外で頑張り通す理由がなくなってしまう。わたしは“お告げ”を受け入れることにした」(前掲 「ダライ・ラマ自伝」 P.217)。 3.2008年3月の暴動の真実の姿を明らかにすることが重要。 今回のチベット調査旅行では、ラサのセラ寺の奥深くまで入ることができ、110年ほど前に、日本人僧の河口慧海が修業したという僧院を見て回ることができた。僧院内の壁には、河口慧海の修行中の写真が掲げてあった。それを見て私は、彼の著作を読めば、当時のセラ寺の様子を知ることができると思った。私はただちに彼の「チベット旅行記」(全5巻 講談社学術文庫刊)を読んでみた。 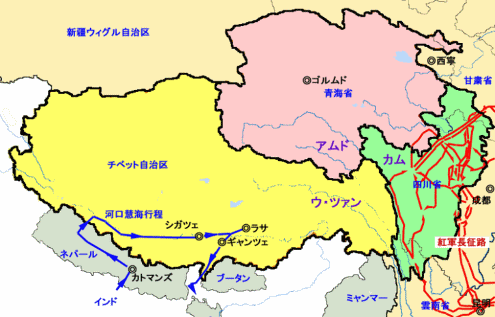 そして私はそこに、120年ほど前にラサで起きたある事件の記述を発見し、びっくり仰天した。その事件が、2年前の暴動とそっくりであったからである。それは第2巻のP.184〜186に記述してある。全文を引用したいのだが、長文になるので要約をして以下に記す。 「120年ほど前、ラサの商売はネパール人に牛耳られていた。あるとき、ネパール人経営の商店で、チベット族婦人が万引きの疑いをかけられ、辱めを受けた。それを耳にし怒ったセラ寺のラマ僧千人(後述の壮士坊主)ほどが、刀などを持ってネパール人の商店街を襲った。ラマ僧たちはネパール人の商店に乱入し、店を叩き壊し、商品や金銭を奪っていった。そのとき、ラサ市内にうろついていたチンピラも加わって、いっしょに乱暴狼藉、略奪を行った。その後、これが国際問題となり、チベット政府がその賠償をすることになり、しかもネパールの兵隊が24、5名、ラサに駐在することになった」 私は2008年3月のチベット暴動の真相を、「セラ寺などのラマ僧の一部の極左派が仕掛けた破壊活動に、チベット族若者の中のチンピラが付和雷同し、彼らが漢族商店の破壊、略奪、暴行を行った。それが武装警察や人民解放軍の大弾圧を誘発したもの」と、捉えている。これがあの暴動を、2年あまりの歳月をかけて調査してきた私の結論である。(ただしこれは私見であって、今回の調査団の共通見解ではない)。なお暴動当日のラサの様子については、大木崇氏の労作「実録 チベット暴動」(かもがわ出版刊)を読めば一目瞭然であるが、残念ながらこの「貴重な歴史の生き証人」の本はあまり世間に認知されておらず、あの暴動の真相はいまだに誤解されたままであると、私は考えている。 もちろんラマ僧や若者の暴発の理由については、さまざまな見解があるが、起きた事態については、120年前の事件と同類であると考えている。今、中国政府にも肩入れせず、チベット人にも味方せず、色眼鏡を外して、あの事態を冷静に見直してみることがたいへん大事なことではないかと考える。 今回のチベット調査で、チベット仏教会の長老(活仏)たちと懇談する機会があった。私は居並ぶ活仏たちに、「なぜあのとき若い僧侶が暴発したのか」と質問してみた。活仏たちは、しばしの沈黙の後、互いの顔を見合わせながら、なにやら協議を続けていたが、そのうち代表格の若い活仏がおもむろに口を開き、「多くの若いラマ僧が地方から、このラサに勉強に来ている。彼らは勉強が終わったら地方に帰らなければならないのだが、地方には帰りたくないのでラサに留まっていた。その若い僧たちが不満を爆発させたのである」と答えた。さらに私は、「セラ寺では蜂起のため、若い僧の一部が武器を準備していたと言われているが、それは本当か」と、質問してみたかったがそれはやめた。なぜなら彼らから本当の答えが返って来そうにないと思ったからである。 私は、ダライ・ラマは「愛と非暴力」を掲げてノーベル平和賞をもらったほどの人物であるから、たとえ味方の陣営でも暴力を振るった輩については、破門に等しい態度を取るべきだと考えている。それが言行一致というものではないだろうか。しかしダライ・ラマは、「チベット青年会議」などの暴力を肯定している連中を野放しにしていた。つまりダライ・ラマには彼らをコントロールすることができない状態に陥っていたといえる。 今回、ダライ・ラマの自伝を読んでいて、1959年3月の暴動においても、同様の事態が起きており、ダライ・ラマが大衆をコントロールすることができない状態に陥っていたことがわかった。当時、ラサにはチベット東部のカム地方からの難民の流入が続いていた。すでにカム地方ではカムパ族と中国軍との激しい戦闘が開始されていたからである。カムパ族の一部はゲリラとしてカム地方の山中で戦っていた。まずカム地方で戦端が開かれたのは、中国軍にとってそこがラサへの進路であり、当然、平定しておかねばならない戦略的要地であったからである。しかし私は、それ以外にも大きな理由があったと考えている。 長征時、労農紅軍はこのカム地方を通り、このカムパゲリラに悩まされ続け、しかも彼らとの戦いでかなりの兵士が命を落とした。中国軍にはその怨念が残っており、まずこのカムパゲリラを掃討しようという狙いがあったに違いないと考えている。現在、日本でチベットの歴史を扱った本が数多く出回っているが、この長征時の労農紅軍とチベット族との戦いに言及しているものはほとんどない。私は一昨年以来、現地を歩いて、その痕跡を探し出し、自らの仮説を検証しようとしたが、おりからの地震で道路が寸断されていたり、暴動関係地域のため外国人の通行が禁止されていたり、現地に詳しい案内人がみつからなかったりして、断念せざるを得なかった。幸い今回の調査旅行のガイドが、カム地方出身者であり、長征時のことについても詳しい人物であったので、彼に頼み込み、年内に現地踏破調査を敢行することにした。 とにかく1959年3月時点で、ラサには1万人を超える難民が流入してきていた。その上、モンラム祭典に地方から参加し帰らないでラサに留まっていた僧侶や民衆が、数千人はいた。それらの大群衆が、ダライ・ラマを中国軍から守るという名目でノルブリンカ宮殿を取り巻いたのである。当時の状況をダライ・ラマは、「そのときまでに離宮をめぐる雰囲気が極度に緊張していた。離宮の内壁の外には興奮して、怒りに燃えた大群衆がいた。彼らの大半は、棒切れ、鋤、ナイフまたは彼らが集め得たあらゆる武器で武装していた。彼らの中にはライフル銃、若干の機関銃、または14、5門の迫撃砲さえ持った兵隊たちやカムパ族たちがいた」(前掲 「チベット わが祖国」 P.242)と書いている。そしてダライ・ラマはこれらの民衆の代表に会い、「代表全員に行動を思いとどませるように、最善を尽くして説得した」が、彼らはそれを聞き入れなかった。つまりこの時点で、民衆はダライ・ラマのコントロールが不可能な状態に陥っていたのである。ダライ・ラマの説く「愛と非暴力」の言葉は、怒りに狂った民衆の心には届かなかったのである。その結果、ダライ・ラマは亡命という戦術を取った。あのときダライ・ラマは、大群衆を破門し、毅然として「愛と非暴力」を貫くべきだったのである。 4.チベット人企業家の育成。 今回のチベット調査団の団長の大西広京大教授はチベット問題について、「チベットの問題は、この“企業家”に上昇できる者が少なすぎるため、“企業家は漢族”、“労働者はチベット族”というふうに本来は社会階級間の矛盾であるものが“民族矛盾”として現象してしまっているということにある」(「チベット問題とは何か」 かもがわ出版刊 P.37)という見解を発表している。私もこれにはまったく同感であり、チベット人の企業家の育成こそが、喫緊の課題であるという認識も一致している。当然のことながら今回の調査でも、チベットの企業調査がかなりのウェイトを占めていた。これらの調査結果については、大西教授や同行者の論考が、随時、京大:東アジアセンターのニュースレターに発表される予定なので、重複を避ける意味もあり、私の拙い企業調査報告は省略する。 私は日本の中小企業家として、「チベット人企業家の育成のために何ができるか」を考えてみた。チベットには宗教学は当然のことながら、それ以外に独特の医学・薬学・哲学・天文学などが発達している。したがってこれらを企業化することがまず近道だと思う。 たとえばラサ市内では、冬虫夏草の商売を行う店や回族商人がきわめて多い。一昔前、馬軍団という陸上競技チームが一世を風靡したとき、そのスタミナ源としてこの冬虫夏草が紹介され、一度に有名になった。私もこのとき、この名前を知った。またマラソンなどの競技には高地トレーニングが有効だということは論を俟たない。したがってラサではちょっと高すぎるかもしれないが、競技トラックや宿泊施設を作って、冬虫夏草と共に売り出したらどうだろうか。 ラサにはポタラ宮などの観光資源も整っているから、観光事業も有望である。最近では青蔵鉄道ができ観光客が増えている。今回、私たちはチベット第2の都市シガツェにも足を運んだ。その途中には息を呑むほど美しいトルコブルーの湖があった。氷河も見ることができた。これはすばらしい観光資源である。しかしチベット観光には致命的なネックがある。高山病である。ほとんどの人がこれにかかる。今年も日本人観光客が6名、すでにこれで命を落としているという。私はこれを逆手にとって、チベット医学とセットにした観光旅行を企画したらどうかと思う。病院兼用のホテルを建て、ラサに到着したら、すぐそこに入院し、医者に診てもらい、高山病対策を行う。同時に他の病気も発見してもらう。観光兼簡易人間ドックというわけである。身体頑健で自信満々の人でも、高山病には勝てないので、ラサに入ったら必ず2日間ぐらいは、どうせホテルでゴロゴロして体を慣らさなければならないのである。この間を利用して人間ドックを行えばよいと思うのだが、いかがなものであろうか。またチベット薬学を応用した薬で、現代病に挑戦してみるのもおもしろいのではないか。 現在、チベットに日本料理屋はない。ラサには年間、かなりの数の日本人観光客が訪れている。そして日本人は一様に高山病に苦しむ。彼らが慣れない中華料理やチベット料理を前に食欲不振となっているとき、美味しいうどんやソバに出会ったら、日本人は生き返ると思うのだが、いかがなものだろうか。だれか日本の観光業者と提携して、日本料理屋を始める人はいないだろうか。いずれにせよ、私のような今にも潰れそうな中小企業経営者が考えていても、それは“ごまめの歯ぎしり”程度にしかならない。ここは世界平和のために、トヨタを始めとする日本の誇る巨大企業に、採算を度外視してでも、お出ましを願いたいものである。 5.僧院の実情と改革の必要性。 私は若いころ、1週間ほど禅寺に寝泊まりしたことがある。またその後も座禅を組んだり、禅寺の食事作法に従い精進料理を食べたりした。高野山に霊媒を訪ねたこともある。日本の名僧100人の「遺喝の書」を研究してみたこともある。インドの仏教の聖地を巡礼し、ベナレスで沐浴もした。またヨガ道場で1週間の断食に挑戦したこともある。現在、松村先寧雄先生が仏教の曼荼羅に着眼し、そこから案出されたマンダラチャート思考法の研究も行っている。これらの体験から私がつかんだものは、清廉・静寂・清潔という仏教イメージである。 かつて私は青海省のラプラン寺を訪ねたとき、ちょうど祭礼にぶつかり、それを見学したことがあったが、そのとき僧院の入り口に、僧侶の百足近い靴が乱雑に脱ぎ捨てられている光景を目にして、びっくりしたことがある。まさにそれはカルチャーショックだった。   青海省 ラプラン寺:僧侶の脱ぎ捨てた靴 ギャンツェ 白居寺:脱ぎ捨てられた法衣 今回も、ギャンツェの白居寺の中で、乱雑に脱ぎ捨てられている法衣を見て、同様に驚いた。またどの僧院でもラマ僧は体を揺り動かしてお経を唱えており、何回見てもそれにはなじめない。日本の僧侶は、背筋を伸ばし微動だにせず、読経を行うからであり、それが仏僧に対する私の固定イメージになっているからである。 また今回、僧院の出入り口近くで、信者や礼拝者の目をまったく気にしないで、一生懸命お賽銭の勘定をしている若い僧侶を見た。また僧院の中庭で、談笑しながら、ペッと痰を吐く若い僧侶の姿も見た。総じて僧院は汚く、トイレは鼻をつまんで大急ぎで用を足さなくてはならないほど汚かった。これらは清廉・静寂・清潔というイメージとは程遠いものであった。日本のお寺では、僧侶の修業の基本はトイレ掃除である。これが一般社会にも広まり、「社長が率先してトイレ掃除を行う会社は、繁盛する」という思想まで生まれているほどである。また日本の僧侶は率先して、地域の清掃などの奉仕活動なども行う。チベットの大方の僧院の周辺にはゴミが散乱しており、僧侶たちが清掃活動にいそしんでいる光景などついぞ見かけなかった。 日本とチベットでは、国情や国民性、風俗習慣などがまったく違うのだから、僧侶の生活を比較することは無意味である、そういって物事を片付けてしまうこともできる。それでも私は、同じ仏教にその源を持ちながら、なぜこれほどにその姿が隔絶したものになってしまったのかと、素朴な疑問を抱かざるを得なかった。私は、この疑問を解くためには、どこかの僧院内で、若い僧侶たちとしばらく起居を共にして、その生活を垣間見てみる必要があると思った。また昔の僧院はどうだったのだろうか、ひょっとしたら僧院が荒れ、汚くなったのは文革以降のことではないだろうか、などとも思った。 そこで私は、昔の僧院の状態を知るために、河口慧海が書いた110年ほど前のセラ寺についての記録を読んでみた。河口慧海は「チベット旅行記(三)」で、当時のラサ市内やセラ寺について、きわめてリアルに描いている。たとえばラサ市内には、人糞がいたる所に溜まっており夏場は臭くてたまらないとか、僧侶を含めてほとんどの人が用を足しても手を洗わず、またその手でツァンパ(チベット人の主食の裸麦の粉から作るダンゴ)を握って食べるとか、その不衛生なことを書き立てている。 中でも私が注目したのは、僧侶に大きく分けて二つの種類があり、その一つは修学僧侶で、もう一つは壮士坊主であるという記述であった。共に地方の僧院からラサに出てくるのだが、修学僧侶とは学費や教材費、家庭教師代、宿舎費などが払える層であり、彼らはセラ寺でおおむね20年の修行を積んで、相当の地位となり自分の寺に帰る。もちろん長期にわたる学習に耐え切れず落ちこぼれる僧侶もいるが、その場合でもたいていは金を積んでその地位を得るという。問題はもう一方の壮士坊主である。彼らは修学資金をまったく持たずに地方から出てくるので、まずラサでアルバイトしてその金を稼がなければならない。彼らは修学僧侶や高僧の下僕や警護役になったり、僧院内の供物の整理、僧院の楽隊、田畑の耕作などを受け持っており、そして暇な場合は、山の中へ入って体を鍛えることに専念しており、そこではしょっちゅう喧嘩が起きるという。結局、壮士坊主はアルバイト稼業に明け暮れてしまい、まともに学業を身につける者が少ないと、河口慧海は記述している。 さらに河口は、ラサで最大のモンラムという祈祷会の際には、ラサ中に泊まっている2万5千人ほどの僧侶が集まってくるが、本当の僧侶というような者は誠に少なく、壮士坊主とかあるいはそこで振舞われるバター茶が目当てで来る僧侶が多いと書き、だからお経を読むのではなく、鼻歌なんか歌う奴もあればあるいはその中で腕相撲などを取っている奴もいるという。 私は河口慧海のこれらの指摘を読みながら、それは現代にも通じており、かつての壮士坊主に匹敵する輩が、2年前の暴動の主役を演じたのではないかと思い、現在の僧院内の僧侶の状況を記述した本をくまなく読んでみた。しかしその解答をみつけることはできなかった。やはり僧院で泊り込み、若い僧侶と生活を共にする以外に、若い僧侶の暴発の真因をつかむことはできないと思った。しかし今回の調査団では日程の問題もあり、なおかつ個人行動は慎むべきだったので、それは不可能であった。そこで私は、まず今回、なにかの仕掛けをしておき、次の機会にそれを実現しようと考えた。 6.チベット民族文化の保存。 今回の調査旅行では、ラサ入りした日から3日間、ヤルツァンポ大酒店(雅魯藏布大酒店)に宿泊することになっていた。このホテルが高山病対策では、ラサ市内でいちばん優れているということだったからである。同時にこのホテルは、博物館が併設されていることでも有名であった。かつて日本のNHKテレビでも、このホテルのことが放映されたという。私は滞在中、このホテルの2階にある博物館をじっくり見て回った。そこには国家2級文物に指定されている仏像や法器、骨董品、民具、宝石、祭礼用の面や衣類、マニ車、古刀、古銃などが、数多く陳列してあった。これらの展示物は、このホテルのオーナーがチベット各地の民間から、コツコツと買い集めたものであり、宿泊客の中の購入希望者には販売もするという。 私の目には、他の公的博物館に勝るとも劣らない逸品が並んでいるように映った。ひょっとしたら文革期に僧院から盗み出されたものが、民間に隠されており、それがオーナーの手に渡ったのではないかと、勘繰ったりもした。売り場の担当者の話では、展示物はそこそこ売れているようで、いずれにせよこのままではこの博物館に陳列してある仏像や宝物は売却され、世界各地に散逸してしまうのではないかと思われた。 それらの展示物を見て回っていたとき、私の目に一つの異様な仏頭?が飛び込んできた。売り場の担当者に詳しいことを聞いてみると、それは活仏のしゃれこうべを利用した法器であり、頭頂部を開けてそこに酒を入れて、仏前に供えるもので、金剛頭と呼ばれているという。   私はガラス越しにじっとその金剛頭を見続けた。翌日もその場所に行って、金剛頭と無言の対話をし続けた。そのうちふとその金剛頭が私に、「自分の寺に帰りたい」と語りかけているような気がした。そこで私はその金剛頭を買い求め、それが使われていた元の僧院を探し出し、そこへ寄託しようと思い立った。これだけの逸品ならば、それは可能ではないかと思った。そして同時にその手づるで、その僧院へ潜り込み、しばらくそこで若い僧侶といっしょに修業させてもらおうと考えた。そうすれば若い僧侶たちの考えがはっきりつかめると思った。 その金剛頭は、なかなかの値段で、博物館側もおいそれと値引きはしなかった。数日間にわたる幾度かのきびしいやり取りの結果、交渉は成立した。私はその金剛頭をあらゆる角度から何枚もデジカメに収め、その出身寺を探すために、その画像を関係者に見せたが、それは簡単なことではなかった。時間も限られていたので、私はどこの僧院でもよいので、とにかく預かってもらおうと決め、仏教協会にその旨を申し出た。ところがそれはあっさりと断られた。仏教協会には今までにこのような申し出も多く、これで5回目だという。そしてそのすべてを断ってきたという。どうやら仏教協会はそれで贈収賄関係ができるのを嫌っているように感じられた。結局、私のたくらみも見透かされたような感じであった。現在、私はその金剛頭を、オープン間近の北京の西藏文化博物館への寄託を申請中であり、北京の友人宅に預かってもらっている。 この金剛頭は、もし私の目に飛び込んで来なかったら、おそらくどこかの誰かに買われて、寂しくチベットを離れていったことだろう。私は日本や中国のお金持ちが基金を作って、ヤルツァンポ大酒店の展示物を買い占め、それをそれぞれの出身の僧院に戻して欲しいと、心から願う。そうすればチベットの文化財の散逸が防げるのではないか。私がそのようなヤワな考えを博物館の担当者に熱く語ると、彼はにやりと笑い、「その僧院の僧侶たちは、またこっそりそれを売りに来るかもしれませんよ」と、言った。 チベット文化財の保護と同時に、日本人の私たちがしなければならないことは、チベット文化を日本に紹介することであると思う。私は今、チベット人哲学者プンツォク・ワンギェルの著書を翻訳してもらっている。私は阿部治平先生の大著「もうひとつのチベット現代史」(明石書店刊)で、プンツォク・ワンギェルのことを知った。その本を読んで、彼の数奇な運命に感動すると同時に、彼が獄中で「弁証法新探」という書物を著したというくだりに強く惹きつけられた。阿部先生によれば、このプンツォク・ワンギェルの本は、あの深遠なチベット哲学とヘーゲル哲学、そしてマルクス主義を融合させた最高傑作であるという。さらにプンツォク・ワンギェルは毛沢東やダライ・ラマからも深い信頼を勝ち得た人物であり、あの「17か条の調印」のときの通訳の重責を果たした人物だったという。私はそんな立派な人物が著したこの書物を、ぜひとも日本語訳で読んでみたいという強い衝動に駆られた。さっそくその本を取り寄せ読んでみたが、さっぱりわからなかったので、現在、阿部治平先生と大西広教授の力に全面的に依存して、この書物を翻訳している。もちろん完訳後には、出版するつもりである。おそらくこの本は、たいして売れないだろう。しかし日本にチベット文化の高い水準を紹介することはできると思っている。以下にダライ・ラマ自身のプンツォク・ワンギェルへの高い評価を抜書きしておく。なおプンワン氏は北京で存命中である。 ・「プンツォク・ワンギェルは中国語を自在に操り、毛主席とわたしの素晴らしい通訳を務めてくれた。彼は非常に有能で、物静かで賢明な、思慮深い人物であった。また実に誠実かつ正直な人柄で、一緒にいてとても楽しかった」 (前掲 「ダライ・ラマ自伝」 P.146) ・「わたしはプンツォク・ワンギェルを党書記としてチベットに配属するよう要望した」(同 P.181) ・「もうずいぶんの年だが、プンツォク・ワンギェルはまだ健在だ。亡くなる前にぜひもう一度会いたいと思う。経験豊かな老チベット人コミュニストとしてわたしは今も彼を高く評価している」(同 P.182) 7.文化大革命期の清算。 「私は学生時代、日本で、文化大革命に翻弄された」と、私が中国人に話すと、ほとんどの相手が目を丸くする。現在、中国には文革の被害者と加害者が同居し合っている。彼らは罵りあい、殴りあい、殺しあった仲である。私も日本で殴られた。その恨みは今でも忘れない。中国では人民大衆の中にも、指導者の中にも、この憎しみが沈殿している。 チベットも例外ではなく、文革期には大混乱に陥り、チベット人同士が敵味方に分かれて戦った。ラマ僧たちの中には、この文革期に三角帽子をかぶされ、市内を引き回され、命を落としたものもいる。残念ながら、日本で発行されているチベット関連本には、この文革期のチベットの状況を詳しく報じたものは少ない。今回、私は活仏たちに、「あなたたちは文革期を、どのように過ごしていたか」と、短刀直入に聞いてみた。比較的若い活仏が、「私は15歳だった。下放されて地方の農場に行っていました」と答えた。私は彼の隣に座っていた老齢の活仏の返答に期待していたが、彼は微笑を浮かべただけで何も答えなかった。私は彼もきっとひどい仕打ちを受けたのだろうと思ったが、彼がかもし出す穏やかな空気から、私の質問(詰問)には、彼は微笑みしか返さないだろうと悟り、それ以上の質問をやめることにした。 今回の調査旅行では、高山病に備えて、ラサに入ってから丸2日間の休養かつ禁足期間が設定してあった。私はこのときの退屈しのぎのために、10冊に及ぶチベット関連本を持っていった。その中の1冊に、「殺劫 チベットの文化大革命」(ツェリン・オーセル著 藤野彰・劉燕子訳 集広舎刊)があった。昨年買っておいたのだが、分厚い本で、しかもタイトルが劇画的だったので、まったく手をつけていなかった。深夜、頭が痛くて眠れなかったので、小型の酸素ボンベに口を当てながら、この本を開いてみた。そしてしばらく読み進めて行くうちに、この本に吸い込まれ、頭の痛さも酸素ボンベのことも、すっかり忘れてしまった。この本は、私が今まで読んできた数多くの文革関連本の中でも、最高傑作の部類に入る。 著者のオーセルの父親は写真家であり、文革期のチベットの人間模様をくまなく画像として残した。本文中には、三角帽子をかぶされ、ジェット機の格好をさせられた被害者のラマ僧やインテリ分子、その側で棒を持って殴りつけている加害者の紅衛兵や翻身農奴、また寺院を破壊している紅衛兵の姿など、無数の写真が掲載されている。これほどの写真が残されていたことに、私は驚きを感じると同時に、文革の生の姿を残してくれたオーセルの父親に心の中で手を合わせた。 しかもさらに驚いたことは、オーセルがこの写真を証拠として、そこに写っている人物を丹念に尋ね歩いたからである。すでに死んでしまった人、自分の行為に頬かぶりをして政府高官になっているもの、自分の行為を恥じて仏門に入ったものなど、この本の中で彼は、それらの人の実名を明かして追及している。これだけの証拠が揃っていても、現在のチベットでは文革期のことを総括しようとする機運は生まれていない。私は、加害者は被害者に人間として謝罪すべきであると考えているし、寺院を破壊したり宝物を略奪したりした人間は、私財を投じて償うべきであると考える。あの文革期には中国全土でこれと同じ現象が起きていた。日本でも起きた。せめて仏陀の精神が色濃く残るチベットだけでも、文革関係者は自分の行為を懺悔してから死の床につくべきではないか。もちろんあと20年もすれば、文革期に生きた人間は死んで、この世から消えてなくなる。しかし当事者たちが、しっかり自らの愚挙や暴挙を反省しておかねば、再びそれが起こる可能性がある。 もちろん文化大革命にも、光の部分と影の部分がある。最近、「文化大革命を権力闘争の面からだけではなく、階級闘争の面から見なおす」、あるいは「文化革命は、人間発達の重要な一部分であり、文化大革命はそれを担っていた」また「文化大革命がインフラ整備など、中国経済に与えた影響を再評価すべきである」、さらに「一般大衆の文化財の破壊活動などは、毛沢東の文革思想とは相反するものであった」などの見解が出てきている。残念ながら私は文革の当事者=被害者であるため、どうしても文革を怨念の立場から見てしまう。そろそろ文革を第3者の目で、冷静に見ることが必要なのかもしれないとは思っている。 |
| |